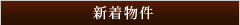
- 淵野辺本町4丁目新築戸建
淵野辺駅 4,780万円 - 淵野辺本町4丁目新築戸建
淵野辺駅 4,580万円 - 淵野辺本町4丁目新築戸建
淵野辺駅 4,580万円 - 【長期優良住宅】上矢部4丁目新築戸建 1
矢部駅 4,480万円 - 東大沼2丁目新築戸建 1
古淵駅 4,180万円 - もっと見る
東京都の木造密集問題の解決には一人一人の住民と話し合うことが大切。
投稿日:2013年10月4日
2013年10月4日の日本経済新聞の経済教室に掲載された日本大の山崎教授の「木造住宅密集の解消を」の論文は、あまりにも浅い建築業界知識と薄っぺらな住宅文化論・都市計画論によるもので、「政府介入による強制収用」という非現実的な暴論になっています。
東京都の木造住宅密集地域問題の2020年までの解消という目標に必要なのは、「政府介入による強制収用」ではなくて「政府補助金活用による個々の建物の耐震化・不燃化火リフォームを全棟に対して行う」ことです。それを政府・東京都・民間業者の3者が一体となって住民目線で進める必要があります。
東京都の「木密地域不燃化10年プロジェクト」実施方針が平成24年1月に出されていて、それをもとに山崎教授が論文を展開しているのですが、この実施方針全体として「東京を美しい防災都市にするにあたって、貧しい都民の貧しい木造住宅が邪魔だから、仕方ないのでお上が救ってやる」的な徳川幕府のような感覚で貫かれています。
この木密プロジェクト・実施方針の14ペー目の「3 木密地域の住民への働きかけ等」において、「(1)地域密着型の集会の開催」、「(3)住民への情報提供等」という項目があります。これは「意見を聞く会を開いてやるから、それで満足しろ」といことと「危険度マップなどの情報を出してやるから、自分でなんとかしろ」といっているのです。
だいたいこの実施方針の対象は「整備地域約7000ha」です。普通は「○○棟、○○世帯」なのですが、「上から目線」の計画で、一人一人のことは見ていません。戦争後の建物で築50年の既存不適格の建物に住んでいる後期高齢者単身世帯で年金暮らしの人のことなどかまっていられないのです。それでは計画が進むはずがありません。
「お金の無い貧乏老人」でも、立派な日本国民であり、日本国憲法の第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」の基本的人権の生存権を持っているのです。戦争後にそこに住み、高度経済成長時代には寝る時間も惜しんで働き、気がついたら70歳を超えて年金暮らしで、住んでいる家は「バラックで既存不適格だから潰す。マンションに建て直すけど、あなたの土地は小さすぎて等価交換できないから、金を2000万円用意するか、家賃10万円払って」と言われて納得できる人がいるでしょうか。
六本木ヒルズを立てた森ビルの社長のように、一軒一軒何十回となく訪問して、酒を酌み交わして、個々の地権者に納得してもらうことが必要です。それができるのは民間の地場の不動産業者でしょう。政府・東京都・大学の先生の「上から目線」では不動産は動きません。
東京都の木密問題を解消することは必要です。そのためには民間の地場の不動産業者に権限を与え、個々の住宅・地域事情に合った実施方針を作り、耐震化・不燃化リフォーム補助金を上げるとともに、地域住民共同住宅の建築の場合には東京都の都営住宅とするなどの政策を行わなければなりません。
東京都の木密問題の対策として「政府介入による強制収用」なんて、ヒットラー並の暴論でしょう。落第です。即刻、大学教授をやめてください。
- トラックバックURL
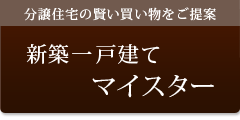
 地域から探す
地域から探す