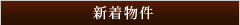
- 淵野辺本町4丁目新築戸建
淵野辺駅 4,780万円 - 淵野辺本町4丁目新築戸建
淵野辺駅 4,580万円 - 淵野辺本町4丁目新築戸建
淵野辺駅 4,580万円 - 【長期優良住宅】上矢部4丁目新築戸建 1
矢部駅 4,480万円 - 東大沼2丁目新築戸建 1
古淵駅 4,180万円 - もっと見る
消費増税後の消費マインドと物価予測のレポートは混乱している。
投稿日:2013年9月21日
大和総研が「消費増税と消費マインド・物価予測」レポートを発表しました。それによると「消費マインドは悪化するが、その後もとに戻る可能性が高い」「物価が上がると予想する人が高止まりする」としました。
このレポートのサマリーとしては
「◆最近消費者マインドの低下を示す指標が表れているが、1989年の消費税導入時や1997年の税率引上げ時の状況を見ると、消費税導入・税率引上げ前には景気動向とは逆に消費者マインドが悪化した一方、駆け込み需要が発生した。導入・引上げ後は、直後に消費自体は反動減が生じたものの、消費者マインドは改善し、やがて消費も改善した。」
「◆今回も、消費税率引上げを巡る議論が既に消費者マインドに影響している可能性があるが、消費税率が予定通り引き上げられることが決まれば、消費者マインドは更に悪化・横ばいとなる可能性がある。しかし、必ずしも実際の景気の悪化を示すものではないと考えるべきである。また、引上げ後の来年4月以降は、消費者マインドは改善する一方、実際の消費は一時的な反動減を見せるものの、その後、元に戻る可能性が高い。消費者マインドの改善の度合いは、再来年10月に更に2%引き上げられることもあり、完全には元に戻らない可能性はある。」
「◆消費者による物価予想については、過去においては、消費税導入・税率引上げが明確になった後、実際の物価動向には関係なく、物価が上がるとする人が急激に増え出し、実際の導入・引き上げ後に急減した。今回も物価が上がるとする人は既に9割近くなっており、消費税増税予定が既にかなり影響している可能性がある。仮に予定通りの引上げが決まった場合、来年4月までは「上がる」とする人は高止まりするとみられる。その後、一旦低下する可能性はあるが、その度合いや更にその先については、円安・原油高・金融政策などの動向はもちろん、再来年10月予定の再度の消費税率引上げにも左右されると考えられる。」
これは大変わかりずらいサマリー(要約)となっていて、よくわかりません。その理由の一つが前回の消費増税の分析において政治経済状況などを加味して分析してしまったために、今回も様々な要因で考えざるをえなくなってしまったためです。
前回の消費増税後にアジア通貨危機があり金融危機があり政変などもあったためにそれらを変数として加えてしまうと、消費者の景気マインドと実際の物価動向という2大要因の影響度が低くなってしまったので、解析がとても複雑になってしまいました。
それと消費者のマインドをとても低く見ていることがあります。前回の消費増税の時には無かった「景気ウオッチャー」という庶民レベルの消費マインド調査を経済理論的に未成熟であるがために軽んじています。ただ、これは現在の行動経済学では理論づけられていませんが、結果として他の経済指標よりもかなり正確に消費者行動を表しています。
それは前回の消費増税の時には無かったSNSなどの影響を加えていないために理解できないのです。一人のアルファーブロガーの書き込みが消費財の売れ行きに大きく影響する時代であること理解しなければいけません。
また分析において「多変数重回帰分析」ではなく「単回帰分析を複数行う」やり方でやってしまったためです。これではそれぞれの指標がなぜそうなったのか、その影響因子は何なのかが反映できません。そのために、それらを影響因子を全て指数として含んだものしにしないと「分析のための分析」になってしまい。「三次データ同士の相関をとる」という統計学としての致命的欠陥をしらなかったようです。
結論から言うと、
1.消費増税後に消費マインドは後退する。
2.物価は上がる
になります。
その理由は、所得が増えない中で可処分所得が減れば家計の中で減るのは「こずかい・遊興費」です。これは消費マインドに大きく影響します。自分で自由に使えるお金が減るのですからマインドに影響しないわけはありません。
物価は、電気代とガソリン代が上がっていて、さらに関連する項目へも影響していくために確実に上がります。これらは消費者が選択できるものではないので消費マインドとは関係なく上がるのです。
ということで大和総研のレポートは参考にならないものです。大和総研は行動経済学の理論を探求し「定性データの定量化」を急がなければいけないでしょう。アルファーブロガーの消費への影響力を定数化しなければなりません。
- トラックバックURL
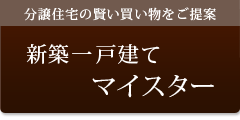
 地域から探す
地域から探す