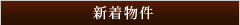
- 淵野辺本町4丁目新築戸建
淵野辺駅 4,780万円 - 淵野辺本町4丁目新築戸建
淵野辺駅 4,580万円 - 淵野辺本町4丁目新築戸建
淵野辺駅 4,580万円 - 【長期優良住宅】上矢部4丁目新築戸建 1
矢部駅 4,480万円 - 東大沼2丁目新築戸建 1
古淵駅 4,180万円 - もっと見る
公立高校の難関大学合格者のトップ10。都立御三家含めて東京が半分を占めた。
投稿日:2013年5月30日
難関大学への合格者の多い公立高校への進学者が多い中学の学区の土地や分譲住宅価格は高くなる傾向があります。
その国公立高校の2013年4月の東京大学・京都大学・早稲田大学・慶応大学合格者の一覧をまとめてみました。
一番は東京学芸大付属高校となりました。次いで、日比谷高校・浦和高校・西高校と都立御三家など公立有名高が上位に並んでいます。
 一番の東京学芸大付属は卒業生が340名と多いため早稲田大の合格者を168名出していて人数が増えました。単純計算ではほぼ全員が難関大学に行っている計算になります。
一番の東京学芸大付属は卒業生が340名と多いため早稲田大の合格者を168名出していて人数が増えました。単純計算ではほぼ全員が難関大学に行っている計算になります。
そして二位に都立御三家のの日比谷高校が入りました。こちらも卒業生が315名なのでほとんどが難関大学に行っている計算になります。特に重複合格がしずらい慶応大学の合格者が144名と公立高校ではトップとなっています。慶応湘南キャパスなどが近いため目指す人が多いということもあります。
そして三番目に「県立高校の雄」の浦和高校が入りました。卒業生が400名ですので難関大学入学率が上位2校よりも落ちるのと、一時期は東京大学に100名近い合格者を出していたのが半減しいます。立地が埼玉県さいたま市浦和区なために、東京が通学便利ですからどうしても東京大学に行きたい人は東京の私立に進学する人が多いことがあります。さいたま市浦和区の有名中学校のクラスのトップはほとんど開成高校や桜陰にいってしまいます。そのため浦和高校の周辺の住民で東京大学を目指す人で浦和高校に行く人の率が減っているのが要因です。埼京線や南北線などができて東京に通学しやすくなったことも大きいです。
そして六番目に筑波大学駒場がきていますが、ここは卒業生が163名と有名国公立高校では一番少ない卒業生なために人数としては、その実力より低くみられがちですが、東京大学の合格者が103名なため卒業生の63%というとんでもない高さです。難関大学合格者数が284名なので卒業生163名が1.7校合格しているということで、東京大学の滑り止めで早稲田・慶応に合格しているという数字になります。実質的に国公立のナンバーワンです。
私立の中学高校の一貫校が難関大学の合格に有利と言われている中、公立でこの数字は素晴らしいものです。スーパーサイエンスハイスクールという文部省の指定活動をしていて中高一貫のカリキュラムが効果を発揮していると言えます。やはり公立でも中高一貫が学力向上には良いようです。
そして、難関大学に早稲田・慶応という東京の大学のみをカウントしているために西日本の高校のランクインかが少ないてので、京都大学の合格者の多い公立高校を抜き出すと、大阪・京都・滋賀と近畿圏の高校が上位にきました。これは公立高校ですと、どうしても学習塾の影響が強くなり、そこに通いやすい立地が重要となるため、大都市近辺が有利になってしまいます。
そのため公立高校のトップ10は首都圏と愛知のみで、京都大学の上位をみても関西圏のみとなってしまいました。20位以内には、岐阜高校や浜松北(静岡)や前橋(群馬)などが入っていて大変健闘していると言えます。
できれば地方の公立が中高一貫校ができると学力の向上が図れて、それが難関大学合格という「勉強の成果」につながりやすくなります。中学の全国一斉試験では地方の県がトップになっているのですから、あとはやり方次第でと思います。
親にしてみれば、学力向上の結果として有名大学に進学して、有名企業に就職できるのが「子育て」の大きな目標でもあります。そこにつなげる工夫を地方の教育関係者が行えば、「地域の住まい価値」が生まれて、子供の進学のために首都圏に移住してしまい地方の価値が下がり、限界集落が発生することが少しでも防げると思います。
新築一戸建て分譲住宅が大都市圏に集中していて、首都圏・中京圏・近畿圏だけで全体の8割をしめています。これは、このようなことが背景にあります。「教育の成果」が全国等しくなれば、全国的に分譲住宅が建設されるようになり、土地の価値も全国的に底上げされることになります。
公立高校の成果はただそれだけでなく、地域の価値まで左右していることを考えて欲しいと思います。
- トラックバックURL
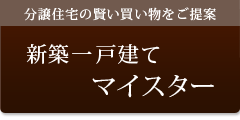
 地域から探す
地域から探す