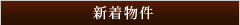
- 淵野辺本町4丁目新築戸建
淵野辺駅 4,780万円 - 淵野辺本町4丁目新築戸建
淵野辺駅 4,580万円 - 淵野辺本町4丁目新築戸建
淵野辺駅 4,580万円 - 【長期優良住宅】上矢部4丁目新築戸建 1
矢部駅 4,480万円 - 東大沼2丁目新築戸建 1
古淵駅 4,180万円 - もっと見る
住宅ローンの金利は依然として市場最低レベルであるが、今後上がるかもしれない
投稿日:2013年5月11日
住宅金融支援機構が住宅ローンのフラット35の5月資金実行分の金利が発表になり、変動金利で1.60%からになり、長期固定で1.810%からになりました。さらに各銀行で優遇プランがあるために実質は変動で1%割れとなっています。
これは依然として史上最低レベルの金利になっています。

1970年からの長期金利の推移をみると、1980年代は7%から8%でした。それが下がり始めてバブルの時に5%まで下がりました。
その後、バブルの精算の「失われた20年」のデフレ経済になり金利はどんどん低下して2003年に「ゼロ金利」となる1%を割、その後は少し上がりましたが再び2012年後半より「ゼロ金利」状態の1%割れになりました。
それが安倍首相がインフレターゲットとして2%を掲げて、それを日銀も掲げましたので、今後は金利が上がる可能性が出てきました。
ただ、住宅ローンの元である長期金利は国債利回りに影響されるのですが、その国債を日銀が買い上げると言っていますので、そうなると国債の市場残高が減り価格が上がりますので、利回りは下がることになるために、この点から言えば住宅ローン金利は現状維持になると言えます。
つまり、住宅ローン金利が上がる要素と下げる要素の両方の政策が現在行われているために「住宅ローンが上がるか、下がるか」はわかりずらい局面です。
■長期金利の決定要因とは
ではそもそも長期金利とはどういう要因で決まるのか。
まず基本的な考え方が「期間構造に対する期待仮説」です。
金融資産の金利と満期までの期間との関係を金利の期間構造といいます。 もしも将来の短期金利の動きが完全に予想できるのであれば、現在の金利の期間構造は将来の短期金利の動きによって決まるはずです。例えば10年間資金の運用を行う場合に、10年満期の国債に投資する場合と、期間が1年の国債を購入して毎年乗り換えるという方法があるが、どちらかの運用方法が有利であれば、残りの方法で運用する人はいないことになります。 こうした意味で、長期金利はその投資期間の短期金利の平均となることが考えられる。これが、金利の期間構造に関する期待仮説です。
ただ実際には、将来の短期金利の動きは予想に過ぎないので、10年間経ってみてその間の短期金利の平均が現在の10年の長期金利と一致するとは限らない。 また、長期間資金を固定することによって別の投資機会を失う危険があることや、政府でも投資期間中に財政が破綻して資金が回収できないという可能性はゼロではない。 このため長期金利は予想される短期金利の平均にリスクプレミアムが上乗せされて決まると考えられる
その他では、「市場分断仮説」があります。
金融市場は短期、長期の2つの市場に分かれており、調達ないし運用する資金の性格が異なるため、一方の市場への参加者は他の市場には参入せず、また両市場間で裁定も行われないというのが市場分断仮説です。 各市場では、それぞれの市場内での資金需給によって価格の決定が行われ、その結果、長短両市場では独自の金利が成立するとされます。確かに、同じ保険会社といっても生命保険会社が扱う資金は数十年という長期資金であり、一方、損害保険会社は1年未満という短い性格の資金を扱っていますから、生保会社は長期市場の主要なプレイヤーですし、損保会社は短期市場で活躍しています。しかし、現実にはどちらの保険会社も長短両市場で活動していますし、長短金利の裁定取引も活発に行われています。 市場分断仮説によれば、利回り曲線がいろいろな形に変化するのも、たまたま各市場内での需給関係の相対的強弱を反映した結果に過ぎず、その間に何らかの法則性を見出そうとするのは無意味だということになりますが、この説はどちらかといえば少数派です。
■長期金利の特徴
ここで素直に長期金利の特徴を考えてみると
①存期間が10年に最も近い国債の金利が日本では代表的な長期金利である。
②物価変動の予測によって左右される
つまり、日銀が国債を買い上げるとなると長期金利のコントロールがしやすいということになり、政府の政策が長期金利に反映しやすいとも言えます。
ただ国債の消化が現在では国内金融機関が9割以上をしめているために日銀がコントロールできるのですが、これが外資の比率が上がることになるとコントロールができなくなるということになります。またそれ以外にもコントロールできなくなる可能性かあります。
その長期金利のコントロールができなくなることがあるのは
①国債を外資が大量に購入してきて国内消化率が下がる
②格付け機関が日本国債の評価を下げた時
③日本政府自体が債務超過となり国債を発行できなくなるもしくはハイパーインフレをもたらしてしまう場合
この3つにおいて一番怖いのが③になります。現在国の借金は1000兆円を超えようとしていますが、まだ資産があるために問題ないのですが、この先に借金が増えて資産が減る事態が続くと、必ずいつかは債務超過となってしまいます。その時には長期金利は跳ね上がることになります。
■今後の金利の見込み
以上のことより、今後の長期金利の見込みを考えると
①日本政府の借金が増えて、破綻まではいかないが、国内国債消化が厳しくなり緩やかに利回りが上がり、ヨーロッパ並みの5%になる。
②日本政府の借金は増えるが、日本経済がトヨタ自動車のように復活して、長期金利はなんとかコントロールできて2000年前後の2%前後で安定推移する。
③日本政府と日銀の歴史的政策が成功し、超低金利が継続して2%以下で超低金利は継続する。
この3つが考えられます。
現在の経済学の常識では①となる確率が高いと言えますが、今回のアベノミクスは「世紀の実験」といわれるようにもしかしたら②とか③があるかもしれません。
ですので今後の金利の見込みとしては、どの立場をとるかによって変わるといえるでしよう。
私としては②になって、金利は少し上がるが1%台で推移してくれるといいなと思っています。
- トラックバックURL
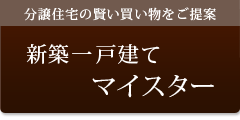
 地域から探す
地域から探す